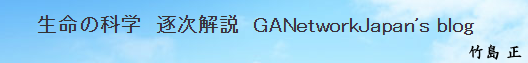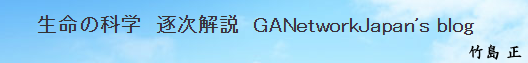 078 Here are a few examples of how the senses disagree. First, let us use this fanciful situation. In a hall seating a thousand people, imagine we have sensitized the floor to the degree where an insect falling upon it would register a sound loud enough to be heard by all; and to implant this information strongly in the minds of those present, we have conducted a number of experiments demonstrating the sensitivity of the floor. So if, by the trick of using heavily padded soles, we have a man walk down the aisle without producing the sound of accompanying footsteps, the following imaginary conversation might take place between our eyes and ears.
078 Here are a few examples of how the senses disagree. First, let us use this fanciful situation. In a hall seating a thousand people, imagine we have sensitized the floor to the degree where an insect falling upon it would register a sound loud enough to be heard by all; and to implant this information strongly in the minds of those present, we have conducted a number of experiments demonstrating the sensitivity of the floor. So if, by the trick of using heavily padded soles, we have a man walk down the aisle without producing the sound of accompanying footsteps, the following imaginary conversation might take place between our eyes and ears.
Eyes: "I see a man walking down the aisle."
Ears: "Impossible! I hear no sound."
Eyes: "But I tell You he is there. He's about half way down."
Ears: "It's your imagination. We both know how sensitive this floor is. I'd hear anyone walking down the aisle."
078 ここで各感覚が如何に互いに意見が合わないかを示す若干の例を挙げましょう。この空想上の状況を採用しましょう。千人の人々が着席しているホールの中で、一匹の虫がその上に落ちても全員に聞こえるようなだけの大きな音が記録されるような位に床の感度を高めたとして、その情報を強くそれらの人々に植え付ける為に、私達はその床の感度を実証する数多くの実験を行って来ました。そこでもし、靴底に厚い当て物をするというトリックを使って、一人の男に足取りに伴って発生する音を出すことなく、通路を歩かせたとすると、私達の目と耳の間で以下の想像上の会話がなされるかも知れません。
目:「通路を歩く一人の男が見える。」
耳:「有り得ない! 全く音がしていない。」
目:「しかし、言って置くが、その男はそこにいる。もう半分の所まで来ている。」
耳:「それはあなたの想像だ。私達二人共、如何にこの床の感度が高いか知っている。もし誰かがその通路を歩けば聞こえる筈だ。」
【解説】
これまでの講座から、私達は自己の感覚に支配された奴隷になっていることを学んで来ました。しかし、感覚反応に自分が完全に組み込まれている為に、そもそも私達自身と自分の感覚との違いを自覚することは難しいのです。また、その心の中の葛藤というものも、突き詰めれば矛盾する二つの感覚の意見に由来するということを本項は示しているものと思われます。
一方、自然界を観ると、動植物達の行動には葛藤や迷いは認められません。草は刈り取られる間もなく、新しい芽を出しますし、虫達は迷うことなく花を訪れ、蜜や花粉を集めるのに忙しく働いています。そこには歓びこそあれ、悲愴感は一切ありません。彼ら人間以外の創造物はもちろん、各々の鋭敏な感覚を有し、それらを各々の生存活動に不可欠なものとなっています。しかし、彼らと人間との最大の違いは、彼らはその存在を100%創造主に委ねているということだと思っています。一瞬一瞬、油断の無い自然界の中で生きて行く彼らにとって、かくも落ち着いて短い各々の生涯をひたすら全うしようとしている背景には、自らを守ろうとする感覚器官以上に創造主に全幅の信頼を置いていることがあるように思えます。
第1部 3章 段落077 [2009-07-29] <<
|
>> 第1部 3章 段落079 [2009-08-04]