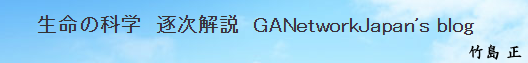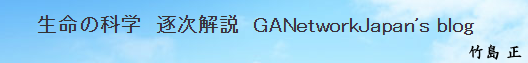 035 The orange tree, wafting its perfume on the southern breeze, need not delve into a laboratory analysis of atmospheric conditions to know that only in the milder climes will it survive. This tender species depends upon natural law to insure its continuation; so nature does not capriciously broadcast its seed in frigid zones, she sows them. where the sun is warm.
035 The orange tree, wafting its perfume on the southern breeze, need not delve into a laboratory analysis of atmospheric conditions to know that only in the milder climes will it survive. This tender species depends upon natural law to insure its continuation; so nature does not capriciously broadcast its seed in frigid zones, she sows them. where the sun is warm.
035 南からのそよ風に芳香を漂わせるオレンジの木は、温暖な気候においてのみそれが生き延びられることを知る為、大気の諸状態を研究室での徹底した分析に出す必要はありません。この繊細な種はその継続を保証するのに自然の法則に依存していますので、自然は気紛れにその種を寒冷地に播くことはなく、太陽が暖かな場所にそれらの種を播くのです。
【解説】
人間の手でなく自然自体がオレンジの木を育てることに関しては、最近、ある方から借りた「奇跡のリンゴ−絶対不可能を覆した農家 木村秋則の記録」(幻冬舎刊、2008年)という、日本のリンゴ農家の話を紹介しましょう。
青森県のリンゴ農家である主人公は、ふとしたことから福岡正信の著書(「自然農法−わら1本の革命」春秋社刊 1975年)に巡り会います。福岡正信(1913-2008)は不耕作、無肥料、無除草を特徴とする自然農法の提唱者として有名な方です。その著書の影響を受けて主人公は自分のリンゴ畑で完全無農薬のリンゴ作りを始めることになります。
しかし、リンゴ作りは多くの農薬が必要とされる難しい農業であり、農薬を使わない主人公のリンゴ畑はたちどころに虫に食われ、葉を落とし、花も咲かない状況に陥ります。もちろん津軽のリンゴ農家ですから、リンゴが成らなければその家の収入は途絶えます。一家は数年で極貧の生活に陥って行きます。その間も研究熱心な主人公は朝となく夜となくリンゴの木と対話し、また悩み貫きます。
その悩みの末、行き詰まった主人公は自らの死に場所を求めて岩木山に登り、まさに木に自殺用のロープを掛けようとした時、あおあおと繁るドングリの木と出会います。肥料も農薬も与えられないドングリの木は健康そのものであり、その木に近付いた時、その周囲の土が柔らかく、豊かなことに気付かされました。それまで目に見える幹や葉の部分だけを見ていましたが、実際には目に見えない根や土の中の状態が重要であることを知ったのです。
しかし、その後も試行錯誤が続き、リンゴ畑を人工の肥料を使わず、大豆を播くことで根粒菌を活用した肥効化を進めたり、様々な試みを行い、遂にはリンゴ畑は一面に花が咲き、完全無農薬のリンゴ作りが実現したというお話です。
この本の中でとりわけ興味深いのは、リンゴの木々や様々な害虫達に主人公が度々話し掛けたということです。例え害虫でも敵視することなく、暖かく接しているのです。これについては、かつてルーサー・バーバンクが棘無しサボテンを開発した時、一つ一つの棘をピンセットで抜きながら、バーバンクはサボテンに「これからは棘は必要ないよ。私が守って上げるから。」と語りかけたことと類似しています。
また、土壌が豊かになるにつれて、リンゴ畑に棲む生物種が多様になってからは、かつてのような害虫の大量発生は無くなったとされていることも興味深いことでした。即ち、多様な生物が棲息することが安定した生物相、調和した世界を構成するとも言えるものです。なお、本書中には何と主人公のコンタクト体験も紹介されていることにも驚きましたが、リンゴの木を含め、自然に対する本書に記述されている主人公の取組姿勢は、アダムスキー哲学の実践例としても優れた内容だと思っています。
以上は日本のリンゴ畑の例ですが、アダムスキー氏が長年暮らしていたパロマー山麓周辺はオレンジ畑が数多く点在しています。そのオレンジの木を眺めながら、この一節が書かれたものと思われます。
第1部 2章 段落034 [2009-05-28] <<
|
>> 第1部 2章 段落036 [2009-06-01]